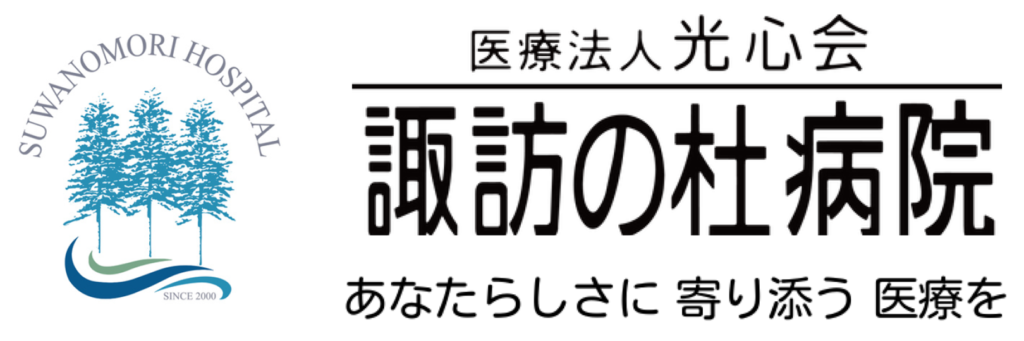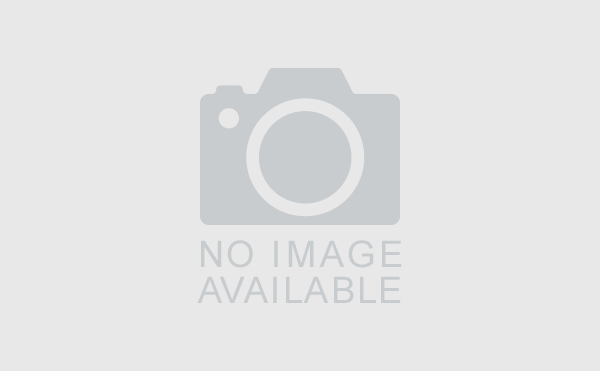Time now(令和7年9月-No.2)「野生動物との共存」
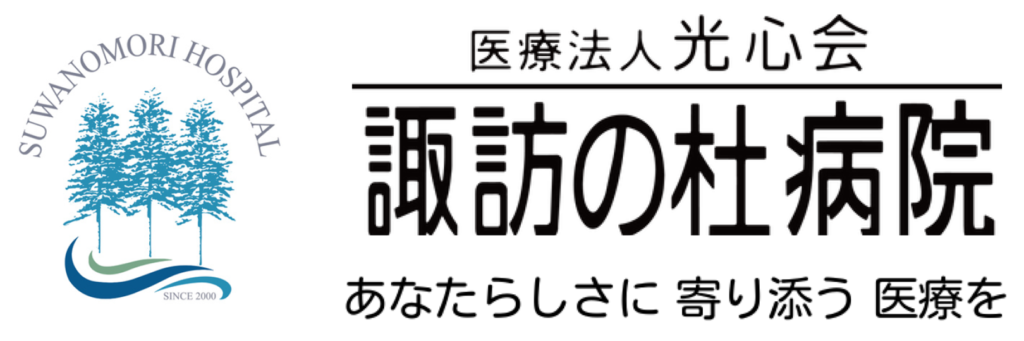
メニュー
インフォメーション
・診療時間
午前 8 : 30 ~ 12 : 30
午後 14 : 00 ~ 17 : 30
※リハ科のみ午後診察時間は12:50~17:30
・休診日
日曜日・祝日
水曜日午後(リハ科のみ診察)
土曜日午後(リハ科のみ診察)
〒870-1121大分市大字鴛野118番地の1

0570-071277
「野生動物との共存」
こんにちは。9月になり朝晩は少し涼しくなってきた気がしますが、日中はまだまだ暑い日が続いています。気温差で体調など崩さないように気をつけましょう。
突然ですが皆さんは『熊』と聞いて何を連想しますか?『くまモン』、『プーさん』、『リラックマ』など…?愛嬌のあるキャラクターが多い熊ですが、ここ最近、日本各地で熊による被害が急増しており、深刻な社会問題となっています。ツキノワグマやヒグマが人里や市街地に出没し、農作物や家畜への被害のみならず、住民や登山者が襲われるといった人的被害も相次いでいます。
2023年と2024年には過去最多レベルの被害が報告され、一部の自治体では「クマ出没注意」だけでなく、「不要不急の外出を控えるように」と呼びかけられる事態にもなりました。特に今年はツキノワグマの被害が里山のみでなく住宅地でも増えている報道が目に付きます。また、今年起きた北海道福島町での新聞配達員や羅臼岳での登山者のヒグマによる死亡事故はショックでもあり、記憶に新しいと思います。
熊による被害が増加している要因の一つは、社会の構造変化が挙げられます。農林業の衰退や過疎化によって里山の管理が行き届かなくなり、人と野生動物の境界が曖昧になったこと。また、温暖化などにより熊の主食であるブナやコナラなどの実が不作になり、餌を求めて人里に出没する傾向が増えること。さらに、自然保護の取り組みにより熊の個体数が回復してきたことなどが、結果として人間との接触リスクを高める要因となっていると考えられます。
こうした状況の中で、登山やキャンプなどの野外活動を楽しむ人々にとっても、熊との遭遇は現実的なリスクとなっています。特にツキノワグマの生息域が広がる東北地方や北アルプスなど中部山岳地帯では、登山道などでの目撃例が後を絶ちません。熊鈴、熊スプレーの携帯や複数人での行動、音を立てるなどの基本的な対策が推奨されていますが、それでも事故はゼロにはなりません。安全な野外活動をするためには、登山者など一人ひとりの意識と行動が重要となります。私も登山を趣味として年に数回、九州以外の山に登る機会がありますが、以前に比べ登山中の熊に対する意識が確実に高くなったと感じます。
一方で、熊が絶滅したとされる九州では、こうした熊被害は現実味の薄い話に聞こえるかもしれません。実際に九州では1957年に大分・宮崎県の県境で子熊の死骸が発見されて以降、九州産の野生のツキノワグマは確認されていません。1987年に大分県の祖母・傾山山系で捕獲されたツキノワグマはDNA解析にて本州から持ち込まれた個体とされおり、2012年には環境省が「絶滅」を公式に発表しています。そのため熊対策への関心や危機感も他の地域に比べて低くなりがちです。しかし、イノシシやシカの数は増えており、日本全体の生態系管理や野生動物との共生を考える上で、地域差を超えた共通の課題として捉える視点が求められます。
熊やイノシシ、シカとの関係は単なる「害獣駆除」で片付けられる問題ではありません。人間と野生動物がどう共存していくか、自然との向き合い方をどう再構築するかが、これからの大きな課題です。登山やキャンプなど野外活動に限らず、日常の中でも、自然や野生動物とどう関わっていくかを考えることが大切です。くれぐれも野生動物には決して食べ物などを与えないようにしましょう。 医療とは全く関係のない話でしたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。最後に8月に奥穂高岳に登った写真を紹介させていただきます。

令和7年9月タイムナウ 医事課 次長 田村岳志
「野生動物との共存」
こんにちは。9月になり朝晩は少し涼しくなってきた気がしますが、日中はまだまだ暑い日が続いています。気温差で体調など崩さないように気をつけましょう。
突然ですが皆さんは『熊』と聞いて何を連想しますか?『くまモン』、『プーさん』、『リラックマ』など…?愛嬌のあるキャラクターが多い熊ですが、ここ最近、日本各地で熊による被害が急増しており、深刻な社会問題となっています。ツキノワグマやヒグマが人里や市街地に出没し、農作物や家畜への被害のみならず、住民や登山者が襲われるといった人的被害も相次いでいます。
2023年と2024年には過去最多レベルの被害が報告され、一部の自治体では「クマ出没注意」だけでなく、「不要不急の外出を控えるように」と呼びかけられる事態にもなりました。特に今年はツキノワグマの被害が里山のみでなく住宅地でも増えている報道が目に付きます。また、今年起きた北海道福島町での新聞配達員や羅臼岳での登山者のヒグマによる死亡事故はショックでもあり、記憶に新しいと思います。
熊による被害が増加している要因の一つは、社会の構造変化が挙げられます。農林業の衰退や過疎化によって里山の管理が行き届かなくなり、人と野生動物の境界が曖昧になったこと。また、温暖化などにより熊の主食であるブナやコナラなどの実が不作になり、餌を求めて人里に出没する傾向が増えること。さらに、自然保護の取り組みにより熊の個体数が回復してきたことなどが、結果として人間との接触リスクを高める要因となっていると考えられます。
こうした状況の中で、登山やキャンプなどの野外活動を楽しむ人々にとっても、熊との遭遇は現実的なリスクとなっています。特にツキノワグマの生息域が広がる東北地方や北アルプスなど中部山岳地帯では、登山道などでの目撃例が後を絶ちません。熊鈴、熊スプレーの携帯や複数人での行動、音を立てるなどの基本的な対策が推奨されていますが、それでも事故はゼロにはなりません。安全な野外活動をするためには、登山者など一人ひとりの意識と行動が重要となります。私も登山を趣味として年に数回、九州以外の山に登る機会がありますが、以前に比べ登山中の熊に対する意識が確実に高くなったと感じます。
一方で、熊が絶滅したとされる九州では、こうした熊被害は現実味の薄い話に聞こえるかもしれません。実際に九州では1957年に大分・宮崎県の県境で子熊の死骸が発見されて以降、九州産の野生のツキノワグマは確認されていません。1987年に大分県の祖母・傾山山系で捕獲されたツキノワグマはDNA解析にて本州から持ち込まれた個体とされおり、2012年には環境省が「絶滅」を公式に発表しています。そのため熊対策への関心や危機感も他の地域に比べて低くなりがちです。しかし、イノシシやシカの数は増えており、日本全体の生態系管理や野生動物との共生を考える上で、地域差を超えた共通の課題として捉える視点が求められます。
熊やイノシシ、シカとの関係は単なる「害獣駆除」で片付けられる問題ではありません。人間と野生動物がどう共存していくか、自然との向き合い方をどう再構築するかが、これからの大きな課題です。登山やキャンプなど野外活動に限らず、日常の中でも、自然や野生動物とどう関わっていくかを考えることが大切です。くれぐれも野生動物には決して食べ物などを与えないようにしましょう。 医療とは全く関係のない話でしたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。最後に8月に奥穂高岳に登った写真を紹介させていただきます。

令和7年9月タイムナウ 医事課 次長 田村岳志
メニュー
インフォメーション
・診療時間
午前 8 : 30 ~ 12 : 30
午後 14 : 00 ~ 17 : 30
※リハ科のみ午後診察時間は12:50~17:30
・休診日
日曜日・祝日
水曜日午後(リハ科のみ診察)
土曜日午後(リハ科のみ診察)
〒870-1121大分市大字鴛野118番地の1

0570-071277